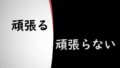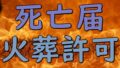Podcast: Play in new window | Download
第76回目のラジオ配信。「花まつり」がテーマです。(BGM:音楽素材MusMus)
2021年の今年は東日本大震災から10年の節目になりますが、また福島宮城では震度6強の大地震がやってきましたね。10年たってもまたあの時の恐怖・不安がよみがえってくるのは、心休まらないことだと思います。今回はコロナ禍の続いている時分なので、10年前とはまた違った苦労があると思います。
さて私のところは四国香川なので地震の影響はまったくなく、地震の翌日の2月14日は全日本仏教会からの今年の花まつりのポスターが届きました。
あっちは大地震で大変なのにこっちは花まつりのお祝いかと、そのギャップを感じたところです。
ところで皆さまは花まつりのイベントをご存知でしょうか。
仏教には大切な日にちが3つありまして、仏教宗派関係なく広くお祝いする日です。
その一つが、今からおよそ2500年前に仏教をひらかれたお釈迦様の誕生をお祝いする「花まつり」です。日本では一般的に4月8日(春八日)にお祝いされます。
あと二つは、12月8日のお釈迦様が悟りをひらかれた日と、2月15日のお釈迦様がお亡くなりになった日です。
「4月8日・12月8日・2月15日」は仏教宗派関係なく、仏教徒であればお釈迦様に関する大切な日として必ず知っておかなければならないのですが、まあ実際には、お寺によくお参りしている人でもうっかり忘れてしまうこともあると思います。
それこそ2月14日は何の日でしょうか。
そうバレンタインですよね。
バレンタインの行事をしない人・興味のない人でも、2月14日って何の日ですかと聞かれると「う~ん。バレンタインかな~」って答えますよね。
翌日の2月15日はお釈迦様のご命日のお涅槃ですが、それは答えられなくても、2月14日のバレンタインは何んとなしに答えられる人は多いと思います。
私が思うに、これはテレビとかお店とかで繰り返しよく宣伝されているかどうかだと思います。バレンタインが近づくとチョコレートやプレゼントを渡しましょうと、テレビやお店のフェアなどでよく見かけるようになりますよね。
そもそもバレンタインが何の日か知らなくても、2月14日にバレンタインがあるんだなあ~と何んとなしに知るんでしょうが、2月15日のお釈迦様の亡くなった日や4月8日のお釈迦様のお生まれになった花まつりは、テレビやお店のように人びとが何度も目にするところで繰り返し宣伝されないので、やっぱり認知度は低いんだと思います。
- バレンタインが何の日?
- クリスマスが何の日?
- ハロウィンが何の日?
とよく知らない行事でも、私たちはテレビやネットや街中で話題になっていたら、流行っているものだとして、とりあえず参加しますよね。
でもどうも、お釈迦様に関する3つの日
- 4月8日の花まつり、生まれた日
- 12月8日の悟りを開いた日
- 2月15日の亡くなった日
は、お寺の発信力、宣伝力、商業的に力を入れていないからか、なかなか認知度があがりません。
全日本仏教会から今年の花まつりポスターが2種類届いて、これから私の寺にも掲示するんですが、おそらくこれだけじゃちらっと流し見するだけで、いつまでたっても花まつりの認知度はあがらないでしょうね。
全日本仏教会では、
- 多くの人にお釈迦さまの誕生日を知ってもらいたい
- みなさんと一緒にお釈迦さまの誕生日をお祝いしたい
と、毎年花まつりポスターや花まつり絵はがきの一般応募をしていますが、応募数もそんなに多くはなく、なかなか認知度が上がっていないと思います。
お寺さんによったら「花まつりは4月8日で新学期・新年度で時期が悪いから、お釈迦様の誕生日祝いの花まつりが流行らないのは仕方ない」という人もいますが、いやいやそれなら、悟りを開いた12月8日やバレンタイン翌日の2月15日はどうなのと私は思います。
花まつりの時期が悪いというのは言い訳で、要は商業的にお金になるイベントかそうでないかの違いだときつい言い方だとそうなると思います。
花まつりのイベントといったら、お釈迦様の周りにお花をお飾りして甘茶をお釈迦様にかけるといったことぐらいなので、ケーキを切るわけでもなく、チョコをプレゼントするわけでもなく、恵方巻きみたいに太巻きを食べるわけでもなく、甘茶をかけるだけではイベント的な消費活動につながらないのだと思います。
仏教に詳しいお笑い芸人の小藪千豊さんがこの2月から4月ごろになると、お釈迦さまの誕生日「花まつり」をするようにと色々なメディアで伝えていますが、やっぱりそれでも花まつりは全体には広がらず、ごく一部の人たちや地域や寺でしか行われていないのが実情だと思います。
日本でお釈迦様の誕生を祝う花まつりは、聖徳太子の伯母にあたる推古天皇の時代にはすでに始まっていたとされるのですが、そんな1400年ほど歴史のある行事であっても、日本人に広まらないのはもう仕方のないことだと思います。
さてこれで今回の2021年2月16日の雑談を終えます。
これから全日本仏教会の花まつりポスターを私の寺でも掲示しますので、もし立ち寄ったらちらっとでもいいのでご覧くださいませ。
かっけいの円龍寺ブログにも載せたいのですが、全日本仏教会のウェブサイトには無断転載禁止とあるので、代わりに全日本仏教会へのリンクを貼っておきます。
ポスター大賞や絵はがき大賞の作品や作者コメントもあるので、ぜひご覧ください。
それでは来週もまたどうぞ聞いてくださいな。
お釈迦さまのお母さん「摩耶夫人」については、2020年4月7日配信の36回目で話していますので、そちらもよろしければお聞きください。
それと最後にもうちょっと雑談です。
私の住む丸亀市金倉町では、毎年花まつりを4月29日の祝日「昭和の日」にしています。
私のところは香川県では珍しいのか、金倉町内には5つのお寺がありまして毎年順々に花まつり会場が変わります。
白い象さんを子供たちが綱で昨年のお寺会場から今年のお寺会場まで引っ張って来て、女の子のお稚児さんの行列がそれを先導します。
単独のお寺が花まつりの行事をすることはあっても、複数のお寺が毎年場所を変えて、子供が象さんを引っ張って、お稚児さんが出て、お稚児さんがお釈迦様の周りで踊りをするのは、香川ではほとんどないそうです。
それでもここ数年は子供の数が減って、お釈迦様の誕生を祝うお稚児さんの踊りができなくなったり、昨年2020年は新型コロナウイルスの流行で花まつりそのものが中止になりました。
今年も4月29日に金倉町での花まつりが開かれるか不明ですが、もし4月29日に象さんを子供さんが引っ張ていたら、花まつりしてるんだなあと暖かく見守っていただけたらなあと思います。
それともう最後に一言。花まつりはお釈迦様の誕生をお祝いする行事ですが、子供の健やかな成長を願う子供のための行事として行われています。なので大人だけが参加するんだけじゃなくて、もしよろしければお子さん主体で参加してほしいなあと思います。
花まつりはお釈迦様の誕生日?
花まつりとは「お釈迦様の誕生をお祝いする日」のことです。
お釈迦様の誕生日が4月8日かどうかは分かりません。
中国や日本など北に伝わった仏教地域では、仏教を開いたお釈迦様が「旧暦の4月8日」に生まれたという伝承に基づいています。
そのため現在の日本では「新暦4月8日」や「月遅れの5月8日」や「旧暦4月8日」といった4~5月に花まつりをして、お釈迦様の誕生をお祝いしています。
タイやカンボジアなど南に伝わった地域では、また別の日に誕生したと伝わります。
- 花まつり
- 灌仏会(かんぶつえ)
- 降誕会(ごんたんえ)
- 仏生会(ぶっしょうえ)
- 龍華会(りゅうげえ)など
花まつりが一般的な名称ですが、様々な別称もあります。
これらの名称は、ルンビニーの花園でお母様の右腋からお釈迦様が誕生した時に、龍が天から飛来して甘露の雨が降り灌いだ(そそいだ)ことと、お釈迦様が歩いた跡に蓮の華があらわれたことの逸話によります。
元々は灌仏会・降誕会が一般的な名称とされたが、明治時代に浄土真宗の僧侶が、桜の咲く時期ということで「花まつり」と呼び、それが宗派問わず広まったようです。
広告 - Sponsored Links
全日本仏教会の花まつりポスター
全日本仏教会(全仏)の「第4回花まつりデザイン大賞発表!」では、2020年に一般募集した2021年の花まつりポスターや絵はがきのデザインの各大賞を掲載しています。また作者のコメントや審査員の総評もあります。
2021年の花まつりポスターと花まつり絵はがきは、こちらのページ「2021年花まつりポスター・絵はがき申し込み受付開始!」より申込できます。
- ポスター代金は各種1枚50円
- 絵はがき代金は無料
- 送料と梱包費は別途必要
- 主要な59の宗派
- 37の都道府県仏教会
- 10の仏教団体
合計106の団体が加盟している日本の仏教界の連合組織(公益財団法人)。
元は1900年に、仏教各宗派の連絡親睦を目的とした「仏教懇話会」から。