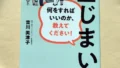真宗僧侶のかっけいです。
図書館で面白そうな仏教書を探していましたら、ショーエンKという現役のお坊さん(住職)が書かれた「ぼうず丸もうけのカラクリ」という書籍がありました。
発行は2009年と今よりも10年ほど前の書籍なのですが、表紙には『時給50万円ですけど何か?』・『そろばん10段、税理士の資格を持つ「現役のお坊さん」がお寺が「絶対もうかるカラクリ」を明かす!』となかなか挑戦的な扇情的な言葉遣いをしているので、内容がかなり気になってしまいました。
読書したメモを書いていこうと思います。

本の目次・構成はどんな感じ。読みやすさは抜群
この書籍は非常に読みやすい構成になっていると思います。
お寺のこと・お坊さんのこと・お金のこと・付き合いのことなどを章ごとに分けられており、その分けられた章の中でさらにテーマを挙げて1テーマ3ページで内容を紹介しています。
ちなみに章はこのようになっています。
- 第1章 お釈迦さまもびっくりする「この世の楽園」
- 第2章 「お金の極楽」はお寺にあり
- 第3章 お寺に隠された「秘密」
- 第4章 お坊さんも大変なんです…
- 第5章 お寺との「お付き合いの奥義」
テーマは40あるのですが、そのうちの30テーマ程度がお金に関わる内容であるので、おそらくですが「ぼうず丸もうけのカラクリ」というタイトルに惹かれた人は飽きずにどんどん読み進めることができると思います。
テーマタイトルもなかなか扇情的です。
- 「時給50万円」が、安心の、即日、現金一括払い!
- 「粗利97%!」のぼったくり
- 「ぼうず頭」で誰でも210万円ゲット
- これが本当の「ぼうず丸儲けのカラクリ」
- 恐怖の「ダブルお布施地獄」
などと読者の興味を引くものばかりです。
お坊さんの私からみた本書の感想
厳しい言い方をしますと読むに足らない内容でした。
本書はじめに著者「ショーエンK」による本書の望みには以下のようにあります。
本書を読んでいただける皆様が、「お寺」と「お坊さん」というものを、より深く理解していただき、今以上に、「お寺」とよりよい関係が築ける一助となることが、本書の望みであります。
本書の原文ママ
お寺とお坊さんというものをより深く理解していただきと言っているのに、本書ではお寺・お坊さんへの誤解が生じるような点も多々見られます。
例えば本書最初のテーマ『「時給50万円」が、安心の、即日、現金一括払い!』であり、文章初めにお葬式のお布施の全国平均は「54.9万円」です。と書かれています
この数字ってどこから出てきたんですかね。出典くらい表記すればいいのに。
そしてこの後の小テーマで出てくるお布施50万円も、この冒頭のお葬式のお布施の全国平均54.9万円から言っている金額だと思います。どこの世の中に、年忌法事などでお布施50万円もされる方がいるのですが、最初に大きい金額を載せてその金額を後々まで同じように違った場面で使うのはおかしいでしょ。
ちなみにこのお葬式のお布施の全国平均54.9万円はおそらく日本消費者協会の『葬儀についてのアンケート調査』から独自に推測したのだと思います。
2007年にあった「第8回葬儀についてのアンケート調査」では、68.4万円でした。
2010年の「第9回葬儀についてのアンケート調査」では51.4万円となっています。
この日本消費者協会の集計方法もメチャクチャで葬儀の施主でない人の報告がかなり占めていますし、葬儀は年間100万件もあるのにデータ件数も数百件程度とデータの信憑性がかなり疑われます。
この著者は僧侶(現役住職)だそうですが、本当に葬儀のお布施をこんなにいただいていますか。
真実を書いていますか。私は葬儀のお布施でこのような高額なお布施を預かったことはないですよ。10~20万程度ですよ。もちろん規模にもよりますが。
他にも不景気で世間では不況の嵐が吹き荒れているのに、お布施は今でも上がり続けていると本書ではおっしゃっています。「お布施バブル」とも勝手に表現しています。
不況の影響を受けないと言っていますが、ショーエンKさんのお寺はすごいんでしょうね。全国の大部分の寺院が維持に苦労している状況で、「不景気でもお布施の金額が下がらない」・「不景気でも関係ない」とよく言えますね。
またショーエンKさんは冗談のつもりで書かれていると思うのですが、ちょくちょく読者をバカにしていませんか。
例えば、以下の文章です。
お坊さんは「布教活動」が大切なんです。信者さんに教えを説くのが使命。
だって……「儲かる」という字は「信」じる「者」と書くのですもの。
私の心が狭いのかイラっとしてしまいました。
どんな人にこの本読んでもらいたいか
お坊さんの私からみたら本書の評価はかなり悪いです。
しかし現代のお寺・お坊さんの姿を軽いタッチで読みやすくテンポよく表現しているのは評価できます。
スラスラと読めて1時間もあれば読み終えることができます。
僧侶から見ればう~んと疑問を感じるところもあるのですが、そうですね・なるほどと感じるところもあります。
私としてはお寺や僧侶に対してある程度の理解がある人が、さらに参考として読んでもらいたい書籍だと感じました。(こんなことを書くお坊さんもいるんだなあという感じで)
お寺のことを何も知らない人がいきなりこの書籍を読みますと、今後かなり偏った目で僧侶とお付き合いすることになると思います。
それもこれもだいぶ扇情的な表現をしているところが多いからです。よく読めばだいぶまともなことも書いているのですが、それが読み手のフィルターで遮断されないのか不安です。
例えば「税金の優遇」です。「最強」・「10の結界」とまで表現していますよ。お布施はお寺に入っている限り「税金」がかかりません。と書いていますし、その後も煽りが凄いわ。「税金ゼロ!」です。って。
これだけ読んだら何も知らない人はお寺がホンマにぼったくりと思うでしょうし、丸儲けと思うでしょうね。税金は普通にかかりますし、むしろ一般家庭よりも多額の税金を納めているほどですのにね。
よく読めば僧侶も税金を払っていることが書かれているのですが、本当にさらっとしか書かれていません。本当にお寺の実情を伝える気があるのだろうか。
さいごに。僧侶への不信感があるのかな。
個人的感想として、ここまでこの本書がユーモアもあり煽りもあり読者の目を引き付けるようにかいてあるのは、多くの人の寺院や僧侶への不信感があるからだと感じています。
お寺やお坊さんに良いイメージがあればこんなにきっついきっつい言い方をしなくてもいいはずですよね。(表紙には金文字で「How do priests get so rich?」、僧侶はどうしてこんなに儲かってんの?と英語で表現していますしね)
しかし実際には僧侶にお布施を支払うことや僧侶の生活態度・様式に疑問を感じている人が多いのでしょうし、未だに僧侶が税金を納めていないと信じている人もいるでしょう。
本来ならば宗教とは人生の宗(支え)となる教えなのに、宗教と接する機会が減り、お金で解決する世の中、自己中心的な世の中になってきており、お布施が僧侶の儲けになっていると思われており、僧侶への懐疑につながっていると感じます。
お寺のこと・お坊さんのことに不信感を抱いたままでは、仏教という宗教に触れることもままならないでしょうし、お寺・お坊さんとお付き合いすることも難しいでしょう。
本書はお坊さんから見ればあまりいい印象を持つことができないのですが、読み物の一つとしては面白いので、読む価値はあると思いました。
お坊さんが一般向けに書いてある本も少ないので、読んでみてはいかがでしょうか。
本書はダイヤモンド社が発行しており価格が1300円+税と結構高額ですが、購入しなくても蔵書されている図書館も多いと思います。私も近くの市立図書館に蔵書されており借りてきました。発行されてからだいぶたちますので、おそらく図書館にあるでしょう。(買うほどの本じゃあないです)
広告 - Sponsored Links
【余談】ショーエンKってどんな人だろうか
ショーエンKさんがお坊さんということになっていますが、本書で現役のお坊さん(住職)と書かれている程度で宗派も不明、寺院の所在地も不明と怪しい感じです。
2011年1月に更新が途絶えていますが、アメーバブログもされているようです。(URL:https://ameblo.jp/shoen-k/)
そのブログでの内容と本書の内容である程度どの宗派のお坊さんなのかは推測できますね。
先に言いますと浄土真宗ではないです。
本書の中で親鸞聖人や歎異抄の文字が出てくるのですが、この著者はブログで総本山で修行と書かれており、真宗10派には総本山は存在しないので、浄土真宗ではないことが分かります。またブログでは縁起物を用意ともあり、明らかに真宗ではないことがわかります。
2009年11月2日のブログに檀家さんと四国88か所巡りをしたことが書かれています。
四国八十八ヶ所は真言宗のお寺以外に天台宗4寺、臨済宗2寺、時宗1寺であり、わざわざご門徒さんとお参りしたということはこの宗派のお寺なんでしょう。この中で臨済宗だけは総本山と言う本山格はないので、臨済宗も除外されます。
これ以上は分からないのですが、本書のあとがきには密教の言葉を引用していますので、真言宗か天台宗ではないのかなっと思います。どちらも総本山という本山格のお寺だらけです。
また本の執筆中に国会図書館に行ったや築地朝食会祭りに参加とブログで報告しているので、おそらく東京周辺のお寺かもしれません。
さいごに、本書がお坊さんによる執筆で、お坊さんの視点から見た、ありのままの、現在のお寺の姿を伝えたいのであれば、ショーエンKというペンネームや宗派名を載せないということをせずに、責任を持って私誰それが書きましたとすればいいんじゃないかなと思いました。正直本当に現役僧侶が書いているのかな?と疑問を感じてしまう読者も出てくるでしょうに。ショーエンって勝縁という戒名(法名)なんだろうか。