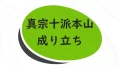Podcast: Play in new window | Download
Subscribe: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Youtube Music
第281回目のラジオ配信。「香川の農具」がテーマです。(BGM:音楽素材MusMus)




かっけいの円龍寺ラジオ
これは香川県丸亀市にいるお坊さん、私かっけいの音声配信です。
農作業の道具の形、農具の形は地域によって形が異なるそうですね。
似ているように見えても微妙に違っています。
今回は、私の家にある二つの農具、讃岐鍬とガンギについてお話していきます。仏教とは関係のないお話です。
讃岐鍬とガンギは実際にみないとイメージしにくいので、この音声をアップロードしているブログの方に写真をのせておきますね。
まずは讃岐鍬の紹介です。
普通、鍬といったら、平らな四角い刃の平鍬、刃の先が三本または四本爪に分かれている備中鍬、刃が肉厚でちょっとでっぷりとした感じの唐鍬が有名ですよね。
他には三角の刃の三角ホー、ツルハシなんかも鍬の仲間とされます。
さて讃岐鍬の形ですが、讃岐鍬は平鍬と三角ホーの間のような形をしています。
平鍬のように四角く平らな刃じゃなくて、かといって三角ホーほど鋭利な三角形ではないです。
もっとゆるやかに刃の先が尖っていて、いうなれば剣先スコップの刃です。
讃岐鍬は剣先の刃がついたものです。
もう一つの特徴があって、刃と柄の角度が急なんですね。
だから備中鍬や平鍬などのように土を耕すのに向いていません。
讃岐の鍬は土を引っ張るとき、畝を作るとき、土を寄せる時に本領を発揮します。
我が家にある讃岐鍬は刃と柄の角度は40度あるかないかくらいです。
耕すのには不向きな鍬ですが、土を寄せる時にはめちゃくちゃ便利な鍬です。
三角ホーでも代用できそうですが、使ってみればわかります。讃岐鍬の方がやりやすいです。
讃岐鍬は刃が寝ていて、それでいて刃の面積があるので、土を滑らすように寄せることができます。畝を作るときには三角ホーよりも圧倒的に楽です。
欠点は土を掘り起こすことができないことですね。
それは平鍬や備中鍬の方が得意です。
讃岐鍬は振り下ろして使う鍬ではなく、持ち上げずに滑らすように使う鍬なので、楽に作業ができるのがいい点だと私は思っています。
他の県の園芸店に行ったことがないですが、香川県の園芸店では、先が尖った剣先型の鍬がたくさん置かれているのがわかると思います。
次に紹介するのはガンギという農具です。
ガンギと言われていますが、どんな漢字を書くのかはわかりません。建物の雁木とか、将棋の雁木とはまた違ったものです。
たまたま言い方が重なっただけです。
このガンギはおそらく見たことがない人がほとんどだと思います。
例えるなら、排水溝の蓋、グレーチングのような、魚焼きグリルの焼き網のような形をした金属がついた農具です。
使い方は二つあって、一つは土の塊を砕くために使います。もう一つは土の表面を均すために使います。
ガンギは珍しい農具だと思います。以前、生成AIに写真をつけて、この農具はなんですかと質問しても、的外れな答えしか返ってこなかったです。
お店に行っても、売られているのを見かけません。
インターネットで検索しても紹介されているサイトがありません。
それくらい珍しい形の農具だと思います。
ただし数年前から、近くにある農家の店しんしんでは見かけるようになりました。
商品名を見ると、ガンギ(土砕き)と書かれていることもあれば、ガンギ(土壊し)、ガンギ(メンタタキ)など、()の中の文字が時々変わっています。
たぶん見ただけだと何に使う道具か分からないからだと思います。
それで使い勝手ですけど、個人的にはおすすめできないです。
なぜかと言うと、まずは耕すことができないからです。土を削って草を抜くこともできません。
大きな土の塊を砕くか、畝を作るとき上と横の斜め部分の表面をならすことしかできません。
土を砕くのが主な仕事なんですが、ガンギの目の間に土が挟まることが多く、思った以上に土を砕きにくいです。また振り下ろすので結構重く感じます。疲れます。
畝の表面をならすにしても、わざわざこのガンギを使う必要性は感じにくいです。
例えば先ほど紹介した讃岐鍬やレーキを使った方がずっとならしやすいです。
魚焼きグリルのような形をしているので、叩きながら畝の側面を整えようとしても、土に当たっている部分が少ないため、平らにしにくいです。
畝の上側の面を整えるにしても、本来は土を砕きながら整えることを想定しているんでしょうが、畝をならすときにガンギを振ると、土の塊を畝の中に押し込むような形になり、土を砕くにはなりません。
そういったわけで、ガンギは珍しい形をした農具なんですが、なかなか土を砕いたり、土の表面をならしたりするには使いにくいです。
私のとこではガンギと言いますが、他の地域でも同じ形をしたこの農具はあるんでしょうかね。
気になります。農家の店しんしんで売られているということは、今でも生産されどこかで使われ続けているんでしょうか。
今回は私の家にある二つの農具、讃岐鍬とガンギを紹介しました。

「がんぎ鍬」というのがあるようです。三本爪の鍬です。
備中鍬のような見た目ですね。
瀧川鉄工所のブログ記事『がんぎを切る』(鍬の鍛冶屋の独り言)で、「がんぎ」とは何かを調べています。それによると、がんぎとは「畑に種を撒く溝のこと」とまとめています。
一方で、三重県総合博物館のウェブサイトではガンヅメ(雁爪)の農具について違った説明しています。
これによると、ガンヅメは江戸時代に久留米藩領の筑後国御井郡国分村の笠九朗兵衛がガン(雁)の爪をヒントに1707年に考案したとあります。
がんぎ鍬もガンヅメも爪が分かれている備中鍬のような鍬で、おそらく鳥の雁の爪をモデルに作った農具なんだろうなあと思いました。
それでいうと、香川の農具のガンギはいったいどんな由来なんでしょうか?
排水溝の蓋グレーチングのような、魚焼きグリルの焼き網のような形のこの農具はなぜガンギなのでしょうか?