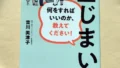Podcast: Play in new window | Download
第298回目のラジオ配信。「賽銭箱」がテーマです。(BGM:音楽素材MusMus)
かっけいの円龍寺ラジオ
これは香川県丸亀市にいるお坊さん、私かっけいの音声配信です。
先日、お参り先で、「儲かってますよね」と冗談交じりで言われました。
はて?
なぜ儲かっているように思われているのか話を聞くと、だってお賽銭箱を設置したんでしょ。とのことでした。
う~ん。どうやら、その方にとってお寺のお賽銭箱はお金が増えていく魔法の箱のような感じなんでしょうね。
今回はお賽銭箱って儲かるのかについて、話をします。
なお、お賽銭に関するお話はこれまでに5回ほどしてきているので、内容が重複するところもあります。
ただどうやら、お賽銭って儲かるよねと言ってきた人がいるように、お坊さんのこと、お寺のことを想像だけでイメージのみで印象を話される方もいます。
例えば、その人は、私に対してブンブン車を飛ばしているよねと言いました。
う~ん。おそらく私の慎重な運転を見たことがないんでしょうね。
きっと荒い運転をするお坊さんを見たことがあるんでしょうが、そのイメージだけで、お坊さん全体お寺全体のことを話されるのは止めた方がいいと私は思います。
それはさておき、今回はお賽銭箱についてのお話をしていきます。
さてお賽銭箱は儲かるのでしょうか。
いいえ、儲かりません。
もちろん儲かっているお寺もごくごく一部あると思います。
ただそれはほんのごくごく一部です。
京都や東京のような人があふれ観光客がたくさんいるお寺、初詣に何十万人・何百万人も訪れるようなお寺であれば、お賽銭で儲けられるでしょう。
しかし地方のお寺ではどうでしょうか。
一日に数人~零人しかお参りに来ないお寺の場合、お賽銭では儲けられません。
お寺に来た人が全員お賽銭を入れる訳でもないですよね。
それに一人あたりの金額だって正確な所は分かりません。
インターネット検索すると、ある神社の平均では70円ぐらい、あるお寺の平均だと10円以下といった情報がでたりします。
一方で、AIに聞くと平均150〜170円と紹介したりと、本当のところ、お賽銭の金額は、人によって全然違います。
皆様が想像するよりも、実はお賽銭の金額はそんなに高くないと思いますよ。
お参りの人数が一日に数人~零人のお寺の場合、お賽銭では儲けられません。
実際、私のお寺の場合を話すと、お賽銭箱を設置したのは、4年前の2021年のことです。
その設置費用を回収しようと思うと、今のペースだと50年はかかるでしょう。
お賽銭箱を設置したからといって、あのお寺は儲かっているなあとイメージされるのは、たんなる思い込みです。
正直言うと、私のお寺は浄土真宗ですが、浄土真宗のお寺にはお賽銭箱が置かれないことが多いです。
というのも、浄土真宗は、仏さまに対して、お願い事をしたり祈ったりしないからです。
もしお賽銭箱があったら、間違った気持ちで仏さまに手を合わすことになるかもしれないですからね。
なので、私のお寺でもこれまでお賽銭箱はなかったのですが、お参りの方からは、お堂の外からでも拝むことができる場所が欲しいとの要望がかねてからあり、そのほかの経緯もあって、2021年から本堂の前に設置したわけです。
浄土真宗の場合、願掛けや祈祷のためにお金を入れるんじゃなくて、仏さまに手を合わすため、お寺の護持に役立てるために、ということで、お金を入れていただければと思います。
ただそうは言っても、実際のところ、賽銭箱で儲けることはできません。お賽銭箱の設置によって、お寺の護持運営に役立つかはかなり怪しいです。
お参りされる方が全員いれる訳ではないですし、入れられるお金の額も実はかなり少ないです。
正直なところ、私はお賽銭箱はない方がいいと思います。
どうして?
儲からないと言っても、数十年後、遠い将来にはいずれ設置費用を回収できるならあった方がいいと思う人もいるかもしれませんよね。
いやいや、それ以上に、お賽銭箱があると、治安が悪くなる可能性を心配しなくてはいけません。
治安が悪くなるというのは具体的には賽銭泥棒やお賽銭箱へのいたずらです。
私の住んでいる香川にはお遍路文化があります。
四国に点在する弘法大師空海ゆかりの88カ所を巡る遍路道には、小さなお堂やお宮さんがたくさんあります。
それらはそこに住む地元の人たちが管理しているお堂で、常には誰もいません。
誰もいないんですが、お賽銭箱がお堂の前に置かれていることがあります。
ある所で聞きました。
賽銭泥棒がひどい、お賽銭箱へのいたずらがひどいと。
ひと月に一度は真夜中に賽銭泥棒がやってきたことがあったそうです。
小さなお堂なので、お賽銭箱も小さいので、元々あったところから離れたところに放り投げられたように捨てられていたそうです。
そこで鎖で箱を固定すると、真夜中にガチャガチャガチャとけたたましい音を遠慮なく響かせてひどく怖くなったそうです。
またある所では、心をひどく悩ませるほどお賽銭箱へのいたずらが加速したこともあります。
もともと、地方の小さなお堂にあるお賽銭箱には、ほとんどお金は入っていません。
ほんのわずかなお金なので、賽銭泥棒が仮にいても、そのあたりに住む人は大事にはしていませんでした。
ああまた賽銭泥棒がいたなあ、元の位置に戻さなくちゃと。
でもお金がほとんど入っていないことに腹を立てた人がいたのでしょうか?ガムやゴミをお賽銭箱の中に捨てられることもありました。
時にはお堂の窓が割られることもあったり、お堂を無理やり開けて、土足で入られたこともあったそうです。
お賽銭箱が呼び水となって、治安が悪くなる可能性もあります。
お賽銭箱からボヤ騒ぎがでたこともあるそうです。
そういったこともあって、お賽銭箱を撤去したところもあります。
お賽銭箱は儲からないものですし、防犯上ない方がよかったりします。
ですがお賽銭箱は儲かる儲からないで設置しているのではありません。
浄土真宗であれば、仏さまに手を合わせるご縁を提供する物であり、そのお賽銭で仏さまをまつる空間を維持していく役割があります。
お賽銭箱の設置が望まれることがある一方で、お賽銭箱があることが逆にデメリットになる可能性だってあるわけです。
だからお賽銭箱があるから儲かっているよね、お金が入ってきていいよね。とは単純にイメージしないでほしいなあと思います。
以上で、今回のお話、お賽銭箱は儲かるものではないですよ、イメージでお話するのはほどほどにね、というお話をしました。
ちょっと余談をすると、ここ5年ほどですかね。令和になってからかな、賽銭箱を設置しないお賽銭と言うのが出てきました。
地方ではほぼ見ることはなく、京都や東京にある有名なお寺でたまに見かけます。
キャッシュレス賽銭やデジタル賽銭というものです。
一例を紹介すると、賽銭箱が置かれていたところに、お賽銭箱の代わりに、QRコードが表示されていて、それをスマートフォンで読み取って金額を入力してお金を入れてもらうやつですね。
何とかPAYとかクレジットカードでお賽銭をできるということで、お金を持たない人、小銭をもたない人に向けたお賽銭だと言われたりします。
それにお賽銭箱がいらないので、賽銭泥棒やいたずらも発生しないわけです。
それだったら、地方のお寺にも導入できるじゃないと思うかもしれませんが、そういうわけにもいきません。
決済手数料はないにしても、そのキャッシュレス賽銭へのアカウント手数料のような物が必要ですし、その会社のさじ加減で、今後の維持費が変わってしまいます。
ほとんどお賽銭がないところでは、維持費の方が負担になるでしょう。
お賽銭をする側からしても、お金を投げ入れるのと違って、お金を送るための画面上の操作をしなければいけないのが面倒に感じる可能性もあります。
キャッシュレスになれてない人、もっといえば、お賽銭は投げ入れるものと考える人もいるでしょうから、抵抗のある人もかなりいると思います。
そんなわけで、キャッシュレス賽銭やデジタル賽銭は地方の方まで広がることはないと思います。
キャッシュレス賽銭やデジタル賽銭はどちらかというと、現金を持たない人のためと言うよりかは、外国人観光客からのお金を期待しているようなのでそういった面から見ても、地方のお寺では必要のないものだと思います。
地方ではキャッシュレス賽銭やデジタル賽銭はいらないでしょうね。物珍しさで設置するお寺や神社はあるかもですが。
- 賽銭泥棒やお賽銭箱へのいたずらが増える
- お賽銭の回収・管理の手間が増える
- 賽銭泥棒やいたずらへの防犯対策に手間やコストが増える
- お賽銭が仏さまへの願掛けや祈祷のお金だと勘違いされる(浄土真宗)
- お堂の外からでも仏さまを拝むご縁になる
- 維持管理のお金として使われる