 僧侶が思うこと・コラム
僧侶が思うこと・コラム 撞木と橦木と鐘木。お寺の鐘つき棒について
お寺の釣鐘の鐘つき棒は撞木(しゅもく)と言います。同じ読み方で橦木・鐘木もあります。これらの漢字違いについて書きます。
 僧侶が思うこと・コラム
僧侶が思うこと・コラム  香り・お香について
香り・お香について  果樹
果樹  お坊さん・私の出来事
お坊さん・私の出来事  お坊さん・私の出来事
お坊さん・私の出来事  寺
寺 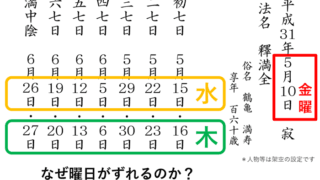 法事法要に関すること
法事法要に関すること  寺
寺 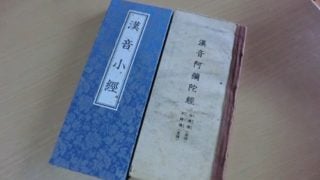 僧侶が思うこと・コラム
僧侶が思うこと・コラム  法事法要に関すること
法事法要に関すること