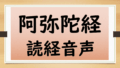Podcast: Play in new window | Download
Subscribe: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Youtube Music
第271回目のラジオ配信。「お寺で葬儀」がテーマです。(BGM:音楽素材MusMus)
かっけいの円龍寺ラジオ
これは香川県丸亀市にいる浄土真宗のお坊さん、私かっけいの音声配信です。
今回は、お寺で葬儀が可能なのかというお話です。
自坊円龍寺では、10年ほど前にお経を納める蔵を解体し、そこに新しくお堂が建ちました。新しいお堂はお骨を納めるだけでなく、法事やお葬式といった仏事ができるお堂です。といったことを、3回前の傅大士像をテーマにしたときに、ちらっと言ったので、それで気になったようで質問を受けました。
結論を言いますと、もちろんお寺でお葬式はできます。
それは自坊円龍寺に限らず、他のお寺さんでも同様にお寺の場所を借りてお葬式をすることはできるでしょう。
気になられる方は、自分とこの檀那寺さん・菩提寺さんに「このお寺で葬儀はできますか?」と尋ねてみてください。
もう少し詳しくお寺での葬儀についてお話しますね。
最近では、お葬式のほとんどは葬祭業者が運営している葬儀会館のことが多いですよね。
私の地域でもここ20年近く、9割5分以上が葬祭業者の会館です。
ひょっとしたらお葬式は葬祭業者を使わないとダメと思われる人もいるかもしれませんね。
でもそんなことはありません。
葬儀はどこでしてもいいですし、誰がしてもいいんです。
ご自宅でしてもよし、地域の集会所でしてもよし、斎場でもいいんです。
もちろんお寺でするのも何ら問題ありません。
もっと言えば、葬祭業者を使わずに葬儀できます。
自治体によっては、自治体独自の葬祭制度というのもあります。例えば私が住む丸亀市だと、霊柩車は3500円、葬儀用の飾りつけ1万円、お位牌や香典帳といった葬祭用品2300円、棺1万2000円、椅子一脚200円などと、自分たちの手で葬儀をするためのシステムを用意しています。
お葬式はどこでもできます。もちろんお寺もそうです。
続いてお寺での葬儀のメリットと、気にしないといけない点について話しますね。
お寺での葬儀のいい点から話します。
お寺という場所は、仏さまを常に安置しおまつりし、そして仏教儀式をするための建物です。
そのため、お寺での葬儀はとても厳かな雰囲気になります。
自坊円龍寺でも、新しくできたお堂でこれまでに何度もお葬式をした実績があります。
それはお寺での儀式が厳かであるのと同時に、先祖のお骨が収められていて、同じ空間で自分たちの葬儀ができるんだという安心感があるからです。
実際、自坊円龍寺では、自分の葬儀をここでしてほしいと生前からお願いされているケースがいくつかあります。仏さまをまつり、先祖のお骨をお預かりしているお寺だからこそ、そういったご希望がご門徒さんの方から出てくるのだと思います。
それとお寺で葬儀をするメリットとして、会場の費用がそれほどかからないというのが傾向としてあると思います。
お寺というのは仏教儀式をする場所です。
そしてそのお寺の建物というのはご門信徒さんたちのこれまでの支えによってできあがった空間です。
なので、仏さまを安置している荘厳壇は初めから備え付けられており、お堂の使用料金は、葬祭業者の会館でする会場費用と比べてそれほどかからないかもしれません。
もちろんお堂の使用料はお寺によって違うでしょうから、確認が必要です。
それではここから注意点のお話です。3つします。
まず一つ目は、お坊さんだけでは葬儀が難しいというお話です。
お寺は葬祭業ではないんですね。葬祭業はやってません。
お坊さんはお寺を守り、仏教儀式を執り行うお仕事をしています。
一方で葬儀全般のことはお仕事としてやっていません。
なので、ご遺体のお化粧をしたり、役場に死亡届などの各種届出をするサービスはしていません。
そういったサービスをしていないのは単純にお寺が葬祭業をしておらず、人手が足りないからです。
補足しますと、葬祭業というのは届け出も許可もいらないお仕事です。なので誰でも自由に葬儀できます。
葬祭ディレクターや仏事コーディネーターのように葬祭業界が独自に葬儀に関する民間資格をたくさん出していますが、葬儀をするのにはそういった資格は何にも必要ありません。
20年ほど前に映画『おくりびと』でご遺体を棺に納める「納棺師・湯灌師」が有名になりましたが、あれも民間による名称です。納棺師や湯灌師でなければ棺に納められないといったわけではまったくないです。
それはそうですよね。葬儀社を使わなくても葬儀はできますし、自分たちの手でご自宅でするさいに、葬儀の届け出許可なんてものもないですよね。
葬祭業のサービスに届け出・許可はなく、誰もが自由に葬儀できます。が、ただしお寺でする場合は単純に人手が足りません。
なので、お寺で葬儀をする場合、どこかの葬祭業者に助けを借りるということになります。
例えば、霊柩車の用意や納棺などは、葬祭業者の手を借ります。
お寺で葬儀をしても、どこかの葬祭業者を頼むことになるのは覚えておいてください。
ここで自坊円龍寺で昔あったトラブルを1つ紹介しますね。
お寺で葬儀をされる理由の一つに葬儀費用の負担を抑えたいというのがあります。
お寺もその意を汲んでなるべく費用がかからないようにします。
しかし営利事業である葬祭業者によっては、その思いを汲んでくれないこともあります。
喪主が葬儀には知った人しか来ないから受付の帳場はいらないといったのに帳場を設置したり、霊柩車の手配だけでいいから葬儀社からは一名でいいといったのに3人も4人もお寺に来たりと喪主が頼んでいないサービスを当日になって勝手にしたことがあります。
極めつけのトラブルは火葬をした後です。
ご遺族が拾い上げたお骨をお寺に持ちかえり、寺で還骨初七日のお勤めをする手はずでした。
しかしその葬儀社は自分たちの葬儀会館に連れて行ってしまったのです。
喪主はお寺に何も言わなかったですが、おそらく葬儀業者の会館費用や帳場代や人件費を支払ったと思います。
喪主の希望に従わず、頼んでもいないサービスをしたその葬儀社は、今は円龍寺では出禁の葬儀社です。
そういったトラブルがかつてありましたので、今では円龍寺で葬儀をする場合は、信頼できる葬儀社だけに協力をお願いする形になります。
他のお寺さんでも、このお寺で葬儀をする場合の指定の葬祭業者が決められている可能性があります。
二つ目の注意点を話しますね。
お寺で葬儀をする場合は、仏式の葬儀に限ります。
そのお寺の宗派の教義・作法にのっとってお葬式が執り行われます。
なんでもいいから安くできるからという理由でお寺の場所は利用できません。
神道やキリスト教の葬儀はお寺ではできませんので、それは注意点です。
あと基本はそのお寺のご門信徒・檀家さんであるのが、お寺で葬儀をする条件になるでしょう。
特別な事情があって、ご門信徒・檀家さんじゃないけど葬儀をしたことはありますが、やっぱり基本はそのお寺と関係のある人がお寺の場所で葬儀をすることになります。
最後3つ目の注意点です。
お寺の都合が合わない時があります。
お寺は仏教儀式をする所であり、ご門信徒の皆様の信仰の空間です。
お寺で葬儀をするのはお寺の役目としてウェルカムなところですが、お寺は葬儀だけの場所ではありません。
お寺で法事の予約がすでに入っていたり、そのほかの参拝者の予定、そのほかの宗教行事などと、お寺の場所を貸し出せないことがあります。
なのでお寺で葬儀をしたいと思っても、お寺の行事やお寺にお参りに来られる他の参拝者との兼ね合いでお断りせざるを得ない可能性も十分にあるのが注意点です。
それでもどうしてもお寺でする場合、希望する時間よりも大きく時間をずらしていただいたり、日にちを一日ずらすといった配慮をいただくことになります。
少しお話が長くなりましたね。話を締めますね。
葬儀はお寺でもできます。
お寺は仏教儀式をするための空間であり、昨今の高額な葬祭費用の面から見てもお寺でするのは大きな選択肢だと思います。
お寺でする葬儀について、他にもいろんな細かなメリットや注意点がありますが、全部話すとかなり長くなります。またそれぞれのお寺によって事情が違うでしょうから、そういった細かなお話は、実際に自分の檀那寺・菩提寺に相談してみるといいでしょう。
葬儀をするのに特別な許可や届け出はありません。誰でも自由にできます。ただし一連の葬送すべてが無許可無届ではありません。
- 亡くなってから七日以内に、死亡届と死亡診断書(死体検案書)を死亡者の死亡地・本籍地あるいは届出人の所在地の役所に届け出る
- 火葬をするためには火葬許可証が必要で、火葬許可願いは役所に届け出て許可を得る
- 納骨(焼骨の埋蔵)あるいは埋葬をするには、墓地・納骨施設の管理者に納骨埋葬の許可を得て、埋葬許可証を提出する
自治体の葬儀制度による住民サービス
自治体によっては住民サービスとして行っている葬儀制度があります。名称は自治体によって違います。
- 市営葬儀
- 市民葬祭制度
- 規格葬儀
- 市民葬・区民葬など
サービスの内容も異なります。
サービスの中身は、自分たちの手で自宅や地域の集会所でするための葬祭セットの貸し出しのこともあれば、特定の葬祭業者と協定を定め安価に葬儀をすることもあれば、公的な斎場での安価な葬儀プランといったように、自治体によって違っています。
いずれにしても、安価な費用で葬儀費用ができるようになっています。
自治体によっては、祭壇の無料貸し出し・霊柩車の使用無料・火葬安置室の無料・葬祭用消耗品の無料提供をしているところもあります。
87回目(自宅葬とは)の音声配信をのせたページに、自治体の葬祭制度を利用して葬儀費用を抑えることを紹介しました。
これまで香川県では「高松市・坂出市・丸亀市」で自治体の葬祭制度がありました。(善通寺市でも斎場で33,000円の通夜・告別式、22,000円の祭壇利用のサービスがあります。火葬料は市民はもともと無料です)
しかし令和4年(2022)8月1日より、高松市の市民葬儀制度は終了しました。これまではAプラン23万円、Bプラン13万円と安価な葬儀が可能でした。
高松市の公式サイト「市民葬祭制度の終了について」によると、
高松市では、市民のみなさんが一般に広く利用できる制度として、昭和49年より市民葬儀制度を開始してきましたが、近年、葬儀に対する考え方が多様化し、事業を開始した当時と比べ、葬儀の形態も大きく変化していることから、令和4年8月1日をもちまして市民葬儀制度を終了しました。
以上の説明があります。
自治体独自の安価な葬儀を提供するサービスはどんどん失われている印象です。
- 愛媛県新居浜市の公営葬儀(2022年3月終了)
- 埼玉県入間市の市営葬(2025年3月終了)
- 埼玉県日高市の市営葬(2018年3月終了)
- 習志野市の葬祭事業(2020年3月終了)
- 東京都町田市の葬祭事業(2022年3月終了)
一例ですがここ数年でいろんな自治体で葬祭制度が無くなっています。
各自治体の説明によると、「葬儀形態の多様化により、利用率が年々低下している」ことが廃止の理由として挙げられます。
ただお坊さんの私はこう思います。

安価に葬儀ができる自治体独自の葬祭制度の存在を知らない人が多いのではないだろうか?
私は香川県丸亀市に住んでいますが、丸亀市独自の葬祭制度を知っている人はそう多くないように思います。
利用率が年々低下しているのは、制度の認知度不足が原因なのではないでしょうか。市民に対して安価な葬儀サービスがあるということを周知する努力をしてほしいです。