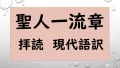Podcast: Play in new window | Download
Subscribe: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Youtube Music
第285回目のラジオ配信。「濁点(゛)」がテーマです。(BGM:音楽素材MusMus)
- 日本図書館協会選定の創作えほん
- 出版社:教育画劇
- 書名:ぜつぼうの濁点
- 作:原田宗典
- 絵:柚木沙弥郎
- 発売日:2006年7月
- ISBN:978-4-7746-0703-0
- 教育画劇への公式リンク『ぜつぼうの絵本』

『ゆめうつつ草紙』(幻冬舎文庫)にて初出された作品を原田宗典氏によって加筆修正、柚木沙弥郎氏によって原画を書きおろされた絵本
『ぜつぼうの濁点』の著者情報より
かっけいの円龍寺ラジオ
これは香川県丸亀にいる浄土真宗のお坊さん、私かっけいの音声配信です。
先日、「ぜつぼうの濁点」という絵本を読んでみてと勧められました。
面白かったので、今回はその読んだ感想のお話です。
最初に絵本の著作情報です。絵本「ぜつぼうの濁点」は、教育画劇出版で、原田宗典が文章を、柚木沙弥郎が絵を書いています。
私がこの絵本を読む前に、私が思ったことを言いますね。
絵本の表紙にはひらがなで大きく「ぜつぼう」の文字が現れています。ぜつぼうの文字は灰色ですが、ぜつぼうの「ぜ」の濁点、てんてんだけがオレンジ色で、目立っています。
そして「ぜつぼうの濁点」というタイトルです。
この表紙を見たときに、私はまっさきに「世の中は澄むと濁るで大違い」の言葉が思い浮かびました。
おそらくこの絵本はこの言葉を知っているかどうかで、見え方が違ってくるのではないでしょうか?
「世の中は澄むと濁るで大違い」は浄土真宗のお坊さんの法話で聞いた言葉です。
- 刷毛に毛があり、ハゲに毛がなし
- 為になる人、ダメになる人
例えば有名なものにはこんな言葉があります。
さらに浄土真宗のご法話で聞いたことがあるのは、
- 意思が濁ると、意地となる
- 口が濁ると、愚痴となる
- 戒が濁ると、害となる
- 本能が濁ると、煩悩になる
- 報恩が濁ると、忘恩となる
世の中の言葉は濁点がつくかどうかで、意味が大きく変わってきます。
それと同じように、良いことを言う口でも濁ってしまうと愚痴の言葉がでてしまいます。
すばらしい戒律があっても、濁ってしまうと悪さ害を及ぼすかもしれません。
本能は生きていく上で大切な存在ですが、それが多くなり濁ると煩悩にまみれ引きずられてしまいます。
浄土真宗のお念仏は恩に報じる報恩なのですが、ついつい私たちは恩を忘れてしまう、忘恩の生き方をしてしまいます。
意思・意地、徳・毒、口・愚痴、戒・害、本能・煩悩、報恩・忘恩とたった一つ濁音があるかないかで、濁りも澄にもなるわけです。
「世の中は澄むと濁るで大違い」という言葉を知っている人にとっては、この絵本は読む前からお話の言いたいことがなんとなく推測できてしまうと思います。
実際、この絵本の内容は想像通りのものでした。
ただお話の進み方・ストーリー性は漸新で面白く、大人でも最後まで楽しめる絵本でした。
ストーリーを紹介しますね。
これは濁点テンテンが主人公のお話です。
ここはひらがなたちがお互いにくっつき合って暮らしている国です。
でもあるとき、濁点が一人ぽつんと道端にいました。
周りが心配して事情を聞くと、ぜつぼうを主にしていた濁点とのことです。
しかしこの濁点は思うのです。
主が不幸なのはひょっとして自分がいるからではないかと。
それで濁点はぜつぼうと離れたわけです。
他にだれか自分とくっついてくれる人はいないのかと、心配してくれた周りのひらがなたちに打ち明けるんですが、みんなぜつぼうといっしょにいた濁点を嫌って去っていきました。
しかしそんなひとりいた濁点の元に、おおきな「おせわ」が押しつけがましく来てくれたのです。
おおきな「おせわ」は濁点を濁った沼まで連れていき、沼のなかへと放り込みます。
濁った沼底に沈んでいく濁点はぜつぼうの主のことを思い、こんな自分と別れることができて良かったに違いないと言い聞かせます。
するとそのつぶやきが「きほう」となって漂います。
「きほう」は早く自分とくっつくように言い、言われるままにくっつくと「きぼう」の言葉となって水面に浮かび上がりはじけました。
そうして、「ぜつぼうの濁点」は「きぼうの濁点」になったのでした。
こんなストーリーの絵本です。読み聞かせるとだいたい10分くらいでしょうか。
なかなか面白いストーリーでしょう。
「世の中は澄むと濁るで大違い」の言葉を知っている人からすると、このお話が伝えたいことは、読む前からなんとなく推測できるような気がしますが、いざ読んでみると、ひらがなを擬人化し、濁点がぜつぼうからきぼうへと主が変わっていく展開が面白く感じると思います。
またこの絵本の絵は柚木沙弥郎さんが書いています。
私にこの本を勧めてくれた人も、柚木さんの絵を見て欲しいから勧めてくれたのだと思います。
柚木さんは2024年に101歳で亡くなるまで生涯現役でいろんな作品を作った人で、染色工芸だけでなく、絵本なども手がけています。
この絵本の絵も、ひらがなを上手く擬人化し、また独特な色合いで、物語を支えています。
ストーリーの面白さと、絵の魅力が合わさって、大人であっても、内容が読む前からなんとなく分かっていても、最後まで面白く読むことができる、そういったすばらしい絵本でした。
機会があったらみなさんもぜひ読んでみてください。
私がいる丸亀市の丸亀市立図書館にも中央と飯山と綾歌に計4冊蔵書があるようです。
有名な絵本のようで、いろんな図書館にあると思うので、お住まいの近くの図書館にあるか調べてもいいですね。