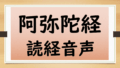Podcast: Play in new window | Download
第27回目のラジオ配信。「病院・病室とお坊さんの姿」がテーマです。(BGM:音楽素材MusMus)
2020年1月は医療ドラマが6本もあるようです。
医療系のドラマは俳優が豪華で、話も一話完結しやすく、最終的には患者を救うという結論に落ちついて、手堅い視聴率がとれるからだそうです。
で、TBSテレビが、金曜ドラマとして1月17日から『病室で念仏を唱えないでください』という面白いタイトルの医療ドラマを始めました。金曜日の夜10時です。
今回は、このドラマをテーマに話をするのですが、第1話放送からまだ1週間もたっていないので、録画をまだ見ていない人もいるでしょう。
ネタバレをしたくはないので、このドラマタイトルから感じることを、お坊さんの私がしゃべっていきます。
ちなみにドラマの大雑把なストーリーは、僧侶であり救命救急医の主人公が、病院で患者を救いながら、生きること死ぬことの答えを見つけようとしている内容です。
さて皆さんはどう感じますか。お坊さんと病院の組み合わせってありえないでしょうか。
たぶん多くの人は、「お坊さんが病院・病室にいたら、縁起が悪い。念仏を唱えるなんて、もってのほか」と答えることでしょう。
実はこのドラマタイトルは、「お坊さんあるある」の言葉です。
でももっと正しく言うと、『病室で念仏を唱えないでください』ではなくて、『病室で念仏を唱えるな』になります。お願いではなく、禁止です。
いつごろか、はっきりとは分かりませんが、いつのころから、お坊さんはお坊さんのかっこで、衣を着た僧侶の姿で病院・病室に行けなくなりました。
聞くと戦前は、まだ病院にお坊さんがお坊さんの姿で行けたそうです。今みたいに、大きな病院・国立の病院ではなく、開業医、いわゆる町医者ばかりだったようです。
顔なじみの人ばかりですので、お寺さんも来たということで、病院・病室にお坊さんがいても何もおかしくなかったのです。
それが戦後になって、お寺の人間は、お坊さんの姿で、病院には行けなくなりました。
今、もしもこのテレビドラマのように、黒い衣を着て、袈裟を首からかけて病院の中に入ろうとしようものならば、立ち入りを拒否されることでしょう。
『病室で念仏を唱えないでください』ではなくて、『病室で念仏を唱えるな』が正しいところです。
黒い衣や念仏は、死を連想するのか縁起が悪いとされるのか、病院から敬遠されるのです。
ここまでの話をきいて、「僧侶のカッコをして、病院に来るなんて非常識」、「お坊さんのパフォーマンスだ」と思うことでしょう。
いえいえ、この黒い衣と袈裟こそ、お坊さんの正装なのですよ。失礼のない姿なのです。
黒い衣と袈裟のあの姿をすれば、お坊さんはどこにでも行くことができます。
皇居の中も入れます。園遊会のようなかしこまった会にも参加できます。国会にも入れます。
当然、各省庁や役場にも行けます。
それこそ知事や大臣に、要望書・意見書を出すときは、お坊さんはきちんと、黒い衣と袈裟を着けますよね。あれはパフォーマンスではなく、お坊さんにとっての正装だからです。
あの姿で行くのが失礼のない姿なのです。
実は結婚式でも、お坊さんはスーツではなく、衣と袈裟を身に付けるのが正装です。
病院だけですよ。お坊さんが黒い衣と袈裟を身につけて、入ることができない場所は。お坊さんにとっての正装がダメだ・来るなとされるのです。
不思議でしょう。
ドラマでは、僧侶である主人公が、お坊さんの姿のまま救急救命室に入る場面があります。しかし現実にはそんなことは許されていません。
一方で話変わると、最近では、「ビハーラ僧」というお坊さんもいます。あまり聞きなじみのない言葉かもしれません。職業名っぽく言えば「臨床宗教師」、別の表現をすれば、お寺ではなく病院で宗教活動をするお坊さんということです。
しかしこの人らも、お坊さんのカッコをしません。スーツや普段着の上に、ちょっと暗めなガウンを羽織ったり、あるいは作務衣のようにお坊さんの作業着を着たりします。
数珠や袈裟は身に付けません。
医療の現場にも、お坊さんが進出することはあっても、お坊さんであることをはっきり示すカッコにはなれないのです。お坊さんにとっての正装であったとしてもです。
私は以前、「お寺には若者が来ない。」「どうすれば若者がくるだろうか」というテーマでブログ記事を書きました。
すると、あるお坊さんがtwitter上で、「なぜ若者が寺に行かないといけないんだ。狭量(きょうりょう)がない坊主だ」とシェアされ、ある程度リツイートされました。
私はtwitterをやらないので、そのツイートにお応えすることはできなかったのですが、浄土真宗僧侶の私は、今でも若者ができるだけはやく寺に来るべきだと考えます。もっと正確に言うと、元気なうちに、まだいつ死ぬとも想像できないような時にこそ、仏法に出あうべきだと考えます。
現在、医療の現場では、ビハーラ僧侶がお坊さんとして活動できる程度です。それ以外だと、たとえ正装でも、お坊さんは僧侶の姿で病院に行くことができません。
ビハーラ僧侶に求められるのは、緩和ケアです。病による痛みや苦しみを医療行為によって治療するのではなく、どうにかして和らげ寄り添っていくかです。要は死を迎えるためのつなぎです。
医療の現場では、お坊さんは僧侶の姿で行くことができません。
現代では仏教が死んだ後での話、お坊さんは死んだ後に世話になることだと思われているのか、病院にお坊さんがいたら、ここにあなたの用事はありませんよという態度をとられるのです。
しかし仏教、特に浄土真宗は生きているときにこそ、大切な教えなのです。大病を患ったり、体が不自由になったり、介護を受けなくてはならなくなってから、「なんでだ。どうしてだ」と愚痴ばかりになってからすがる教えではありません。
しかし現実には、そのように思われていません。若いうち、元気なうちは、宗教なんて関係ない。お坊さんの姿は見なくてよい。となっています。
『病室で念仏を唱えないでください』というタイトルは、ドラマだから皆さん何気なく受け入れて見ていますが、これが現実にあれば、この病院や僧侶は非難ごうごうでしょうね。
毎週金曜日の夜10時からTBSテレビが放送しています。今週1月24日は、第2話です。興味があれば見てはどうでしょうか。
ビハーラとは
ビハーラは、サンスクリット語の「Vihāra(ビハーラ)」のことであり、日本語では「精舎(しょうじゃ)」と訳されます。
つまりビハーラとは、仏教の出家修行者が住する修道施設・寺院・僧院のことです。浄土真宗本願寺派では、「精舎・僧院」の他に、「身心の安らぎ」「休息の場所」の意味も加えています。
ちなみにwikipediaでは次のような説明をしています。
現代では末期患者に対する仏教ホスピス、または苦痛緩和と癒しの支援活動を差す。
「ビハーラ(医療)」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2019年11月23日 (土) 15:51、URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/ビハーラ_(医療)
ビハーラ僧は、患者に対してスピリチュアルな面から緩和ケアをするお坊さんのことです。
今では浄土真宗本願寺派は、「ビハーラ活動養成研修」をして、ビハーラ僧を増やそうとしています。ウェブサイトでは「ビハーラ理念」というものを紹介しています。その中から一部引用します。
ビハーラという言葉は、昭和60(1985)年に、当時仏教大学社会事業研究所にいた田宮仁研究員が、水谷幸正学長と相談し提唱されました。田宮仁氏は、そのビハーラという言葉を「仏教を背景としたターミナルケア(終末医療)施設」の呼称として提唱されました。
この「ビハーラ活動」とは、仏教徒が、仏教・医療・福祉のチームワークによって、患者を孤独のなかに置き去りにしないように、患者とその家族の心の不安に共感し、少しでもその苦悩を和らげようとする活動です。
『ビハーラ理念』浄土真宗本願寺派 社会部より
西洋的な医療行為「ホスピス」とは、別のアプローチをしようとしたのが「ビハーラ」です。
ラジオでも話したように、お坊さんが黒い衣・袈裟と僧侶の姿で、病院に行くことは現実的にはありえない光景です(一般的な認識として)。
しかしビハーラ僧のように、医療現場にも仏教的な考えから、患者に寄り添う行為も増えています。
一方で、次のような否定的なブログ記事がありました。記事タイトルは「ビハーラ僧は、来ないで!(セクシーバディのためのダンシングDIET)」です。内容を短く要約します。
- ビハーラには共感しても、ビハーラ僧が嫌い
- 必要なのは、ビハーラ僧ではなく、寄り添ってくれる人
- 僧侶は病院で活動できたことに満足するが、患者は仕方なく丁寧そうに話を聞いてあげているだけ
- 医者や看護師や介護職員ができないスピリチュアルケアをしているつもりだが、僧侶がいなくてもケアはできる
- 患者に、どれだけ気を遣わせているか知らないのか
- 消毒液に漬けることができない僧侶の衣を着て行っている時点で、医療現場に入る資格はない
なかなか厳しい意見が並んでいますが、このように感じている人も多いはず。
最後にTBSテレビ公式サイト「病室で念仏を唱えないでください」をリンクします。
「生と死をテーマにした」ドラマの魅力や裏話を分かりやすく伝えているので、ドラマを見る前にのぞいてはどうでしょうか。放送時間は毎週金曜日の夜10時からです。
ちなみにドラマ主題歌は三浦大知の「I’m Here」。 “そのままの自分で”というメッセージを込めており、ドラマのために新しく作成したとのことです。