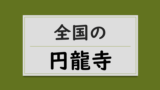Podcast: Play in new window | Download
Subscribe: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Youtube Music
第196回目のラジオ配信。「金倉円龍寺」がテーマです。(BGM:音楽素材MusMus)
かっけいの円龍寺ラジオ
これは香川県丸亀市金倉町にいる浄土真宗のお坊さん、私かっけいが、短いおしゃべりをするラジオです。
今回は自坊円龍寺のいわれについてのお話をしていきます。円龍寺に至った歴史についてのお話です。
私のところの歴史の話なので、面白い話ではないかもしれませんが、お時間あれば聞いてください。
ちなみに円龍寺の創建は1575年で、現在私かっけいの代が24代目となっています。
それと今回のお話は、古い歴史のことで確たるお話ではありません。
円龍寺に伝わる寺伝の他、西讃府志といった古い時代の歴史資料、山本祐三さんが書かれた中讃の山城といった本を参考にお話していきます。
さてそれでは円龍寺の起こりについて話していきます。
円龍寺は香川県丸亀市金倉町にある浄土真宗のお寺です。中讃と呼ばれる香川県の中頃に位置するところで、金倉川という川の近くにあります。
円龍寺の寺伝によると、円龍寺は金倉顕久という人物が、自身の仏道修行のため、出家の寺として建てたと伝わります。
また顕久のお兄さん、金倉顕忠を弔うために、円龍寺の横に西教寺という寺を建てたそうです。
金倉氏というのは現在の丸亀の金倉町や中津を治めていた武士でしたが、元々ここにいた人ではありませんでした。
江戸時代初めに書かれた南海治乱記や玉藻集、江戸時代終わりごろの西讃府誌・全讃史にそのいわれや活動が記されています。
これらの資料によると、当時、丸亀の金倉を治めていたのは、金倉顕忠・中津将監為忠といわれた人物です。
二人の人物が出てきましたが、この二人、金倉顕忠・中津将監為忠は同一人物であると考えられています。
この金倉顕忠と中津将監為忠は、金倉城と中津城というお城を持っていました。
当時は戦国時代で、ここ香川県、讃岐の地でも100を数えるほど城があったようです。
金倉城・中津城は大きな城ではなく、砦というほどの規模だったのでしょうが、金倉顕忠・中津将監為忠はそこを拠点にここ金倉の地を治めていました。
それで話は戻って、さまざまな歴史資料によると、私の先祖は元々この地の人ではありませんでした。
例えば西讃府志によると、
六孫王経基の五男、下野守満快二十一世の孫、三郎左衛門為景、此地に居て、金倉柞原等を領せり。
とあります。
香川の城を調査している山本祐三さんの本によると、中津城、中津氏の系譜は六孫王、つまり源経基の五男である源満快が由来で、1000年頃に摂津からこの地に移ってきたらしいです。
そしてもう一方の金倉城、金倉氏の系譜は同じく六孫王、源経基であり、源経基の長男である多田満仲が由来で、1308年に多田義基が讃岐国多度の荘官に任命されたことによって、この金倉の地に来たとされます。
そんなこんなで、私の先祖とされる金倉城主・中津城主はどちらも源経基が祖であり、同族であるとされます。
そして円龍寺を建てた金倉顕久の兄である、金倉顕忠・中津将監為忠は同一人物であるとされています。
さて、そんな風に、1000年頃と1300年ごろの別々の時期に金倉の地に来た円龍寺の先祖ですが、歴史に名前が出るのが1575年の金倉合戦です。
金倉氏がこの地に影響力があったのは、奈良氏に代わって、この地、那珂郡の代官を務めていたからです。
奈良氏は足利一族の細川氏に仕えていた人で、讃岐守護の細川氏から讃岐の宇多郡と那珂郡を与えられていました。
しかし奈良氏は細川氏に従って京都にいることが多く、金倉氏が代官としてこの那珂郡、現在の金倉川周辺を治めていたわけです。
ちなみに奈良氏の家紋と現在の円龍寺の紋は、同じ剣花菱であり、デザインがとっても良く似ているのも偶然かもしれませんが、関わりがあったことを示す一つにも思えます。
世の中は戦国時代で、1575年、那珂郡金倉の西に隣接する天霧山城主の香川氏に攻められます。これが金倉合戦といわれるものです。
この合戦で金倉顕忠・中津将監為忠は敗れ首を斬られます。
ここで武士としての金倉氏は終わります。
寺伝によると、首を斬られた金倉顕忠には弟がいました。名前を金倉顕久といいます。
金倉合戦のとき、徳島県阿波にいたため助かり、合戦の後すぐにこの金倉の地に戻ってきました。
そして兄を弔うために建てたのが西教寺という寺であり、自身が出家し仏道修行をするために建てたのが、西教寺の真横にある円龍寺です。
これが円龍寺の始まりで、創建が1575年と言われるいわれです。
金倉城の正確な位置は現在も不明ですが、この円龍寺とお隣の西教寺の場所だと伝わっています。
私の寺円龍寺は、金倉顕久を初代として、私かっけいで現在24代目です。
円龍寺には金倉一族の墓と伝わる五輪の墓が今もまつられています。
以上で、196回目のお話、自坊円龍寺のいわれのお話を終了します。
讃岐の一豪族だった金倉顕忠・金倉氏について

音声配信で話したように、金倉町の円龍寺は金倉顕久を初代として、私で24代目となります。
顕久の兄が顕忠であり、ここ金倉を治めていました。
金倉顕忠について紹介します。
金倉顕忠の生きた時代は室町時代の終わりごろ、戦国の時代でした。
ここ讃岐の国(香川県)でも数多くの戦国武将がいました。
その中の一人が金倉顕忠です。
讃岐を治めていた有力武将たち
室町・戦国時代には多くの武将がいました。その中でも讃岐を支配していた武将は次の人たちです。
- 細川家
- 香西家
- 香川家
- 寒川家
- 安富家
- 三好家
- 奈良家
『南海通記』によると、讃岐を主に支配していた細川家の力が弱まると、家臣の三好家が阿波(徳島)を支配し、徐々に香西・寒川・安富らを従えて東讃を勢力下におくようになりました。
対して西讃は天霧山城主の香川家を中心に対抗します。
金倉氏は奈良氏に属していた
私の先祖である金倉氏は、鶏足・那珂を治めていた奈良氏に属していました。
奈良氏は細川氏の家臣であり、細川氏より讃岐の所領を与えられていました。しかし奈良氏は細川氏とともに本領のある畿内にいたようです。
そのため、当時金倉で影響力があった金倉顕忠が那珂郡の奈良氏領の代官をつとめていました。

円龍寺の寺紋と奈良氏の家紋がとてもよく似ているのは、その時のつながりがあるからかもしれません。参考リンク『武家家伝 奈良氏』
金倉顕忠は香川氏と戦った
金倉顕忠は奈良氏に代わり那珂郡を治めていました。特に現在の金倉町に中津城と金倉城を築き、金倉川周辺を支配していました。
この金倉川を境に、東に三好氏が、西に香川氏がいました。
西讃の周辺武将たちは香川氏に服属したが、金倉顕忠はそれに従わなかったとされます。
金倉顕忠が香川氏に従わなかったため、香川氏に討たれることになります。
1575年の金倉合戦で、天霧山城主の香川氏は西から千余人をさしむけ、東からは高松周辺の香西氏らを加えて、挟み撃ちにしたとされます。
金倉合戦により金倉顕忠は討たれ、これ以降奈良氏は讃岐の領地を失い、香川氏が那珂郡を支配します。
金倉氏・金倉顕忠はそもそも誰?
金倉氏についての具体的な資料はほとんどありません。金倉氏が治めた金倉城と中津城も、同一の城と考えられることもあります。
地元の山城研究家の山本祐三さんの著書『中讃の山城』によると、中津城と金倉城は祖先が同じ源経基で別々のときにこの地にやってきたとしています。
そして円龍寺を建てた金倉顕久の兄である金倉顕忠・中津将監為忠は同一人物であるとされています。
金倉顕忠・中津将監為忠についての資料を紹介します。
中津為忠墟
下金倉村川東にあり。鬼屋敷といえり。延宝年間、闕て田畝となせり。相伝ふ、六孫王経基の五男、下野守満快二十一世の孫、三郎左衛門為景、此地に居て、金倉柞原等を領せり。其子為忠将監と称す、武力人に絶たり、自其勇を頼み、驕奢限りなし。人呼んで鬼中津といへり。香川信景と善からず。天正三年信景、香西伊賀守、福家七郎、瀧宮豊後守、羽床伊豆守と相謀り、討て是を滅せり。
西讃府志より
簡単にまとめます。
- 下金倉の川の東に鬼屋敷(中津城)があった
- 延宝年間(1673~1681)に田畑になった
- 源経基(~961)の五男である源満快から21代後に為景という人がこの地にいた
- 為景は金倉と柞原を領地とし、その子供に為忠がいる
- 為忠は香川氏と仲が悪くて天正三年(1575)に滅ぼされた
円龍寺の寺伝では、顕忠(為忠)の弟の顕久が剃髪し、自身の仏道修行のために円龍寺を建立したとされます。そして兄を弔うために隣に西教寺を建てたと伝わります。
寺伝では金倉川の西にある円龍寺が金倉城跡で、川の東が中津城となっています。
金倉氏について書かれた歴史資料
最後に、金倉氏について書かれた歴史資料を紹介します。
天正三年に香川兵部太夫信景より使价を以て香西伊賀守佳清へ申さる々は、奈良但馬守は畿内の地を放れがたくて宇足津に下り来らず、故に奈良が従兵ども恣にして民を虐げ暴逆を為す。新目、本目、山脇の三家は我が旨に従ふ。金倉顕忠、曽て帰服せずして却て其境を犯す。近日、兵を揚げ是を討んと欲す。羽床、福家、瀧宮三家の合力を頼たきの由を通達す。香西氏、是に従ふ。既に香川の家臣、香川山城守、大比羅伊賀守、三野菊右衛門を大将として一千余人を指向らる。香西家の援兵、羽床、福家、瀧宮豊後、同彌十郎、期を同ふして馳向ふ。金倉氏、城を出て切所を搆へ防ぎ戦ふ。五百余人を五手に分て、三手は香川方へ向はしめ、二手は顕忠自ら先を駆て福家七郎に向て戦を始む。彼我必死の勢を出し、曳々声を出して攻戦ふ所に、瀧宮豊後、瀧宮彌十郎が二陣、左右より挟んで是を伐つ。福家七郎、旄を取て攻めかかる。顕忠が兵卒破れて退く。福家が僕従、石若と云者、軽足にて能走り顕忠に追著て、のがさじと詞を懸る。顕忠、駒引返し奴がれめとて馬より飛下り刀を抜て相向ふ。石若、鎗にて渡り合、突倒て首を取り、立上らんとする処に瀧宮彌十郎かけ付け、其首を此方へ渡せと云ふ。石若曰く、左言ふこと勿れ、我が主に奉ると云所へ、福家七郎かけ付て何事をか言と云へば、我が取たる首を奪んとすと云。彌十郎が曰く、我が手先にて取たる首なれば佗方には遣らずと云。七郎聞て、石若が討たる事は隠れなし、首は彌十郎殿に渡せよと下知せらる。石若が曰く、首は遣はすべし、冑は遣はすまじとて持帰る。頸帳には大将金倉顕忠を瀧宮彌十郎手へ討取と云へども、討手は福家七郎が僕従石若が高名と記せり。其時、羽床伊豆守が扱いを以て仲郡は香川方に属し、宇足郡は奈良太郎左衛門に属する也。
金倉賢忠
天正元年三月、那珂郡金倉の郷に金倉賢忠と云者あり。是は細川家の士にて、晴元の代迄は多度郡に居住したり。三好家に成て三好実休に従ひ一家を立しが、今、三好家も乱れて、面々境を争ふ半に、金倉近邊を取て大身に成る可しと思ひ、那珂・多度・宇足津の邊境におしかける。羽床・長尾・香川・奈良等是を悪みて、取ひしぐべきと相定ける。香川山城守信景、西三郡の勢を揃、二千人を以て那珂郡に討て出る。香西方より手合として、瀧宮豊後・瀧宮彌十郎・福家七郎二百余人の勢を以て加勢す。既に合戦始り、香川方柞田・和田・小田・小野・輪佐・大平・山地等一二百の手組を定て、合戦の備へを立にけり。
金倉賢忠、諸手の㕝構ずして、香川信景の旗本へ討て懸る。然所に三野方の勢五百人計にて働きければ、金倉乱て敗北する所を、香西方福家・瀧宮二百人計にて追打にして、苅田の縄手にて賢忠を討取、首数多く取にけり。爰に福家七郎が家人に岩端与兵衛と云者、縄手の勢の中に法師武者に寄合、太刀打して終に与兵衛討勝て、首を取てけり。早軍散しければ、鎧甲・刀脇指迄分取して、従者壱人に取持せ、我は首と甲を持て帰るに、道にて瀧宮彌十郎に行逢てければ、彌十郎其首をくれよと云。与兵衛、仔細に及ばず罷り成ぬよしを申す。彌十郎是非取る可しと、大勢わりかさなりて奪ひけるとき、福家七郎其場へかけつき、何事ぞと尋る。与兵衛申は、我取たる首を奪ひ取申す可しとて此の如しと云。福家が云、其方数度の高名あれば、此法師首何かせん、相渡し候へと云ば、与兵衛、我主の此の如く仰せらるる上は首計まいらする。甲はならずと云て、首を渡しける。瀧宮彌十郎其首を香川信景へ持参して、今度の大将金倉賢忠をば、瀧宮彌十郎討取て候と実検に入ければ、信景大に褒美有て、牛の子山の麓にて十二町の所を瀧宮彌十郎に宛てがはるる。其後福家七郎・瀧宮豊後にも闕所の地五町・十町づつ賜りにき。其後亦那珂郡へ香川信景馬を出し給ふ時、福家七郎も出馬しければ、岩端与兵衛が㕝聞き及たる間、対面あらんとて呼出し、金子等たまはり、日来の手柄聞及たりと褒美之有りて、面目をほどこしける。瀧宮彌十郎大禄は請たりといへ共、貰ひ首取と嘲りしは面目なき次第也。金倉が跡は香川家より仕置し給ふ。今度高名の衆、亦は香川家旧功の衆へ割符して加恩せよと也。
下金倉村川東にあり。鬼屋敷といえり。延宝年間、闕て田畝となせり。相伝ふ、六孫王経基の五男、下野守満快二十一世の孫、三郎左衛門為景、此地に居て、金倉柞原等を領せり。其子為忠将監と称す、武力人に絶たり、自其勇を頼み、驕奢限りなし。人呼んで鬼中津といへり。香川信景と善からず。天正三年信景、香西伊賀守、福家七郎、瀧宮豊後守、羽床伊豆守と相謀り、討て是を滅せり。幼児あり、乳母是を懐にして、其臣西山久左衛門、前川原吉右衛門等と同く、圍を抜て阿州に入り、櫛田村に隠れ居れり。年長るの後、甚太夫忠英と名のり、又此地に帰り、農を業として世を終ふ、其裔今尚ありと云。
今按に金倉顕忠の居趾、彼村にて尋ぬるに知る人なし。圓龍寺西教寺に其墓あれど、正しき伝なければ、証とするべきものなし。爰に為忠とあるが、或は顕忠と同人なるべし。治乱記には、父祖の名を誤りて、其子孫にも用ひたること時々あり。顕忠は為忠が父祖にさる名のありしを伝へ誤りしにもあらん。右にいへる為忠が伝も、治乱記にいふ処の顕忠のことと大にかはりたることなし。今姑く並べ挙て、後考に備ふ。
相云ふ金倉顕忠の弟総左衛門顕久といへるあり、兄顕忠戦死の後髪を薙て一寺を建立。金顕山智浄院と号て天台宗たりしを、蓮如上人に帰依し上人肉筆の名号を本尊と崇して一向に改む。寛永十二年始て木仏を安置し円龍寺と号す。