Podcast: Play in new window | Download
第40回目のラジオ配信。「お経を読む」がテーマです。(BGM:音楽素材MusMus)
2020年5月5日に放送の今回は、前回に引き継ぎ、ご質問にお応えする形でお話をしていきます。
いただいたご質問は「お経はいつ読めばいいのですか?」です。
前回の反省をして質問の答えを先に言いますと、「朝と夕方の一日2回、お経を読むことを、浄土真宗ではおすすめしています」になります。
以下「お経を読む」をテーマにお話していきます。
さてそもそもですが、皆さまはお経が何なのか、ご存知でしょうか。
お経を呪文やまじないだと思ったり、亡くなった人の供養のために読んだりしている人もいることでしょう。
お経を読んで、病気を治したりお金持ちになったりと、お願いごとのためにしているかもしれませんね。
でもお経はそんなもんじゃないですよ。
お経はお釈迦さまがお話になったことを記録した文章です。
お釈迦さまが誰かから質問されますよね。するとお釈迦さまはその人の悩みに対して、対話したりたとえ話をしながら仏の法を説きます。
そのお話したことの記録がお経なんですね。
ですので、お経の中身にはストーリーがあって、お釈迦さまからの生きている人への説法となっています。
お経を読むというのは読んでいる人のために、読まれているんですよ。読んでいる人の口から出た言葉が、お釈迦様からの説法として、私の耳に入るのです。それがお経を読むことです。
さて、浄土真宗では朝夕の2度、仏さまの前でお経を読むことをすすめています。
理由は、今から500年以上昔に本願寺住職の蓮如が、全国の真宗門信徒に対して朝夕2度『正信偈』を読みなさいと決めたからです。だから浄土真宗では朝夕2度だと、今でも言っているのです。
本願寺の蓮如が全国の門信徒に対して、朝夕2度正信偈を読みなさいといったのには、理由があります。
それまでの浄土真宗お坊さんは、仏説観無量寿経や仏説無量寿経、仏説阿弥陀経、六時礼讃といった難しいものばかり読んでいたので、一般の民衆・門信徒は自分の口で、お経を読むことができなかったんですね。
そこで本願寺の蓮如は、浄土真宗の宗祖親鸞聖人が書き残された正信偈に、読みやすいように節をつけて印刷して、お坊さん以外の人も仏様にお参りできる習慣をつけようとされたんですね。
それで朝夕の2度、正信偈を読みましょうとなって、今でも浄土真宗では「いつお経を読めばいいのですか」と尋ねられると、「朝夕に正信偈を読んだらいいですよ」とお応えしているのです。
さて「なぜ朝夕に読むのか」と不思議に思う人もいるでしょう。
朝夕に読むようになった由来は、お釈迦様が説法されていた時代にまでさかのぼります。
お経はお釈迦さまがお話になったことの記録です。ですがお釈迦さまの時代、お話を聞いた人々はそれを文字に残さず、暗記していたそうです。
お経の長さを見ますと、きっとお釈迦さまは30分や1時間、2時間以上とお話をされたでしょうが、お釈迦さまの時代の人は尊い方が話された言葉を、耳で聞いてひたすらに覚えようとしたんですね。
で、お釈迦さまは仏法を学ぶためには「陀羅尼(だーらに)」が必要ですよとおっしゃったそうです。
陀羅尼という言葉は浄土真宗では使いませんが、陀羅尼をわかりやすく言えば、記憶する力のことです。つまり仏さまの教えをいただこうとするなら「繰り返し繰り返し口に唱えて、仏の言葉を忘れないように」というのが大事だったんですね。
それでお釈迦さまの時代、お釈迦さまの説法を聞いた人たちがどうしたかと言えば、一日の終わりに、今日聞いたお話をもう一度自分の口で言い直して思い出そうとするんですね。
間違いなく今日のお話を口にできたら安心して、それで休むんですが、朝になると昨日の話をしっかりと覚えられているか不安になりますよね。
それで朝起きて一番にするのが、昨日の仏さまの言葉をもう一度自分の口で言い直すんですね。
お釈迦さまのお話を再現できてから、一日の食事や仕事がはじまります。
これがお釈迦さまが生きていた時代に、お釈迦さまのお話を聞いていた仏教徒がしていた毎日の日課だったわけです。
私たちがお経を読むことは、自分の口で唱えて、時代を越えて、2000年以上昔のお釈迦さまの説法を耳にしていることです。それはお釈迦さまが生きていた時代の仏教徒が、一日の終わりと初めに、仏の言葉を忘れないように繰り返し繰り返し口にしていたことを受け継いでいるからです。
ですのでいつお経を読めばいいのかと聞かれれば、朝と夕の2度したらいいですよと答えているのです。
ちなみに余談ですが、お経を読むことを「読経をする」と言われますが、お坊さんは仏さまの前でお経を読むことを「おつとめをする」と表現しています。
それは仏さまの前でお経を読むだけでなく、念仏したり讃嘆したりなどもしているからですね。
お坊さんが質問にお答えするウェブサイト「hasunoha」でこんな問いがありました。
対して次の回答がありました。
引用リンク「お坊さんは朝が早いと聞きますが(hasunoha)」
おそらくですが、このお坊さんは「昼夜六時(ちゅうやろくじ)」の意味を間違えていると思います。
昼夜六時とは、昼と夜の6時(朝と夕の6時)ではなく、一日の時間を6つの時に分けることを意味します。ですので、この『観普賢菩薩行法経』の引用部分では、「一日6回、十方の仏さまを礼拝しなさいよ」と書かれているのです。
浄土真宗では「六時礼讃(ろくじらいさん)」と、一日6回、昼夜を6つの時に分けて阿弥陀仏を讃歎し、浄土往生を願いながら礼拝をするお勤めがあります。
- 晨朝:午前6時~午前10時。午前8時ごろ
- 日中:午前10時~午後2時。正午ごろ
- 日没:午後2時~午後6時。午後4時ごろ
- 初夜:午後6時~午後10時。午後8時ごろ
- 中夜:午後10時~午前2時。午前0時ごろ
- 後夜:午前2時~午前6時。午前4時ごろ
一日を6度に分けてお勤めする法要はなかなかありませんが、昼夜六時の時間の分け方は上の通りで、この時間の中でお勤めをします。
こちら「お寺の法要が10時・2時開始が多いのはなぜ?」でも書きましたが、お寺の法要時間は、晨朝や日中や日没と、分けられた時間の中でお勤めするようになっています。
浄土真宗では朝夕の2度、仏前でのお勤めをすすめています。お勤めの参考に、読経音声を2つ紹介します。

浄土真宗では262文字の般若心経を読まない。代わりに日常の短いおつとめとして、220文字の重誓偈(三誓偈)を読経する。浄土真宗僧侶の私が自坊円龍寺のお堂で、重誓偈とお念仏と回向の読経音声を録音しました。

正信偈は浄土真宗で最も親しみのあるお勤めです。読経の練習となるように、有志の真宗興正派僧侶らが録音しyoutubeに音声を公開しました。
上の「重誓偈」は無量寿経の中に出てくる偈文で、5分もあればお勤めすることができます。声は私かっけいです。
下の「正信偈」は浄土真宗の宗祖親鸞聖人が書かれた偈文で、およそ20分間のお勤めです。真宗興正派の有志僧侶らの読経音声で、私も録音に参加しました。







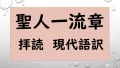


「なぜ早起きなのか」ですが、これは朝のお勤めをするためです
一般的には朝と夕にお坊さんはお勤めをしますが、なぜ朝と夕なのかと言えば、それはお経に書いてあるからです
仏説観普賢菩薩行法経というお経に『昼夜六時に、十方の仏を礼し、懺悔の法を行じ、大乗経を読み、大乗経を誦し大乗の儀を思い大乗の事を念じ、大乗を持つ者を恭敬し供養し、一切の人を視ること、猶仏の想いの如くし、もろもろの衆生に於いて、父母の想いの如くせよ』…とあり「我々仏教とが日々にどんな思いで他者と接するべきか」を教えているのみならずお経を読んでお勤めをする時間の目安として、朝と夕の6時という具体的な指定をされています
私の知る限りでは、朝に早起きしてお勤めをするのは、このお経文から来るものと考えています