Podcast: Play in new window | Download
第121回目のラジオ配信。「硬貨の取り扱い手数料」がテーマです。(BGM:音楽素材MusMus)
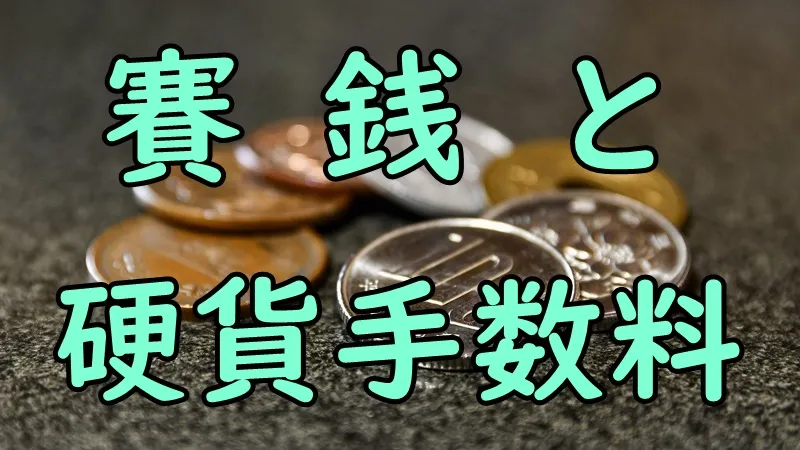
賽銭とは
お礼・感謝の意
國學院大學の記事「なぜ神社では、お金を入れてお祈りをするのですか?」を参考にします。
現在では、神仏への崇敬や祈願の際に供える金銭を「賽銭」と呼ぶ。しかし、字義からは、「賽」は祈願が成就したときのお礼の意味をもつので、本来は、神仏への念願が叶った感謝の意を表すものであった。
「なぜ神社では、お金を入れてお祈りをするのですか?」より引用
3点にまとめます。
- 本来は祈願が成就した時のお礼・感謝の意を表わすもの
- 現在は神仏への崇敬や祈願の際に供える金銭
- これを賽銭とよぶ
國學院とは
明治15年に創設された皇典講究所を母体とし、大正9年に認可された私立大学。
國學院大學には神道文化学部があり、神社本庁が制定した神職資格を取得できる。
似たような大学に皇學館大學がある。こちらは文学部神道学科がある。
皇學館大学は明治15年に伊勢神宮祭主によって設置された神宮皇學館を母体とし、昭和37年に私立大学として認可される。
広告 - Sponsored Links
賽銭・浄財の使い道
寺の護持費として
円龍寺の本堂前の浄財箱、焼香台にお供えのお香料は浄財として、おロウソクやお香、仏花のお供えとして使われます。また境内の維持管理費などにもあてさせていただきます。
全国の寺社仏閣の賽銭も円龍寺と同じように使われていることでしょう。また地域の活動費や義援金として使われることもあるようです。
関連する内部記事










